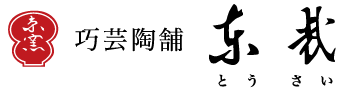品物を木箱に入れて仕立てる場合、箱書きをして東哉印を押します。
この印は落款印(らっかんいん)といって、押す人の名前や雅号である事が大抵です。
この他に別の印が押してある場合があり、これを遊印(ゆういん)といい、引首印や押脚印ともいうそうです。

これは風流な詩句の一節や古語・格言等を印にしたもので、自分の心情や生き方を表したものが多いようです。
義理の祖父にあたる初代陶哉は、気に入った品物に「陶器渡世」と押しています。
”渡世”という言葉に少し身を引いてしまいがちですが、自分はこれで世の中を渡るのだという意気込みが伝わってきます。
父は「此岸翁半(しがんおうはん)」。
あちらの岸である彼岸(ひがん)ではなく、今、生きているこの世である此岸(しがん)で、自分はまだ半分しか生きていない、まだまだこれから…という意を込めています。
二人それぞれ、生き方に対する心構えが違います。

翻って私自身を考えてみると…華甲を向えたというのに、ただ気ぜわしく動き回っているだけ。
これからはもう少し自分を見つめ直して何かカッコイイ遊印をつくらなくては…まだ遅くはないでしょう。
何せ、「此岸翁半」の伜ですから。